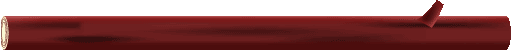
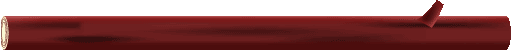
研究紹介
★平成元年〜平成9年度までの論文リスト★
〜昭和63年度までの論文 平成10年度以降の論文
卒業論文
| 年度 | 氏名 | 論文題名 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 高松 直人 | シイタケ原木生産の現状と問題点 |
| 平成2年 | 宇久 真司 | シイタケ原木林施業に関する基礎的研究 −シイタケ原木の形質の観点から− |
| 関ロ 高士 | 森林施業への開空度の応用についての考察 | |
| 冨田 顕数 | 相対幹曲線式を用いた細り表作成に関する研究 −ミズナラのシイタケ原木林施業への応用− |
|
| 渡辺 浩毅 | 長伐期良質大径材生産の現状・問題点について | |
| 平成3年 | 秋山 純広 | 北海道の森林鉄道史に関する研究 |
| 稲葉 芳和 | 冬季におけるエゾモモンガの生息環境と森林 −北大中川地方演習林シンノシケ地区の事例− |
|
| 大廣 真子 | ブナ林の施業に関する基礎的研究 −保育伐のあり方についての考察− | |
| 寺田 宏 | 大型機械による「かき起こし」作業の現状とその課題 | |
| 平成4年 | 上野 俊弘 | 北海道カラマツ林業における長伐期化の現状と問題 |
| 榎本 郷 | 冠形と幹形の関係 | |
| 木下 仁 | 北海道における高性能林業機械導入の現状と課題 −システム導入の作業を事例として− |
|
| 土屋 禎治 | 森林の総合的利用に関する考察 | |
| 松村 秀雄 | 北海道における混牧林施業の現状と可能性 | |
| 米 康充 | 北海道北部における小面積の「破壊−再生」林分の様式 | |
| 平成5年 | 岡田 恭一 | 北海道における伐採量算定方法の推移と現状 |
| 尾張 敏章 | 高性能林業機械の導入が森林に及ぼす影響 −集材路の土壌硬度を中心として− |
|
| 角建 二郎 | 北海道における住宅建築の動向と木材利用 | |
| 幕内 裕二 | 森林資源の有効利用に関する研究 −道産広葉樹中小径材利用の現状と課題− |
|
| 平成6年 | 清野年 |
|
| 外崎 岳司 | 野幌自然休養林の森林施業 | |
| 原田 誠 | ビデオカメラの測樹器への応用について | |
| 平成8年 | 石野 直樹 | ヤチダモ人工林の成長について −北海道大学中川演習林を事例として− |
| 工藤 智美 |
|
|
| 熊井 君子 | 林業の労働災害の現状と課題 −根元的な原因と背景− | |
| 野村 具弘 | 石井山林の森林造成に関する考察 −今後の混交林造成を考えていくために− |
|
| 平成9年 | 神吉 直宙 | ヒトスジシマカおよびリパースシマカと森林タイプの関係 −鹿児島県佐多岬における調査事例− |
| 干葉 君予 | 森林と人間のかかわり方に関する一考察 −東胆振地域を事例として− | |
| 柳本 順 | 刈り出し作業によるトドマツ稚樹の成長 −20年間の推移− | |
| 早稲田 宏一 | 開発地域内の緑地帯が野生動物にとって果たす役割について −勇払平野におけるヒグマの移動実態調査から |
修士論文
| 年度 | 氏名 | 論文題名 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 鎌田 智子 | 道有林における漸伐作業の展開 −沼田経営区川上地方の施業の分析から− |
| 平成2年 | 矢部 恒晶 | エゾシカの生息地管理に関する基礎的研究 |
| 平成3年 | 後藤 竜彦 | 都市近郊林の保全管理に関する研究 −札幌市を事例にして− |
| 平成4年 | 美濃 羽靖 | 森林−人間系に介在する主観的情報の有効的活用に関する研究 |
| 平成6年 | 土屋 禎治 | 北海道有林の経営展開とその構造に関する研突 −北見経営区の事例分析を中心として− |
| 米 康充 | 北海道天然林における再生林分の分布様式 | |
| 平成7年 | 尾張 敏章 | 北海道における高性能林業機械化の進展に関する研究 −素材生産事業体の意思決定要因を中心に− |
| トビアス・ツォルン | Protection Forest Systems in Japan and Gerrnany 日本とドイツの保安林制度に関する研究 |
|
| 平成8年 | サッタル・ニヤズ | 天然林施業体系に関する基礎的研究 −新彊における今後の森林施業の課題− |
博士論文
| 年度 | 氏名 | 論文題名 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 白 乙善 | 韓国国有林における伐出・育林事業の展開に関する史的研究 |
| 崖 麟和 | 韓国における国有林の経営計画と施業の展開過程に関する研究 | |
| 平成5年 | 井上 靖彦 | 地域森林資源の利用に関する研究 −国有林地帯における農民的林野利用の展開を中心として− |
| 平成6年 | 矢部 恒晶 | 野生動物の生息地菅理に関する研究 −知床半島におけるエソシカの生息地利用形態と植生変化 |
| 平成7年 | 鈴木 悌司 | 森林の景観施業に関する基礎的研究 −コンピューターグラフィックスによる樹形生成モデル |
| 平成8年 | 加藤 正人 | 衛星リモートセンシング技術による針葉樹人工林の樹冠疎密度の推定に関する研究 |
| 佐野 真 | 針広混交林のダイナミックスに関する基礎的研究 |
〜昭和63年度までの論文 平成10年度以降の論文
![]()