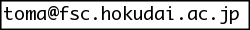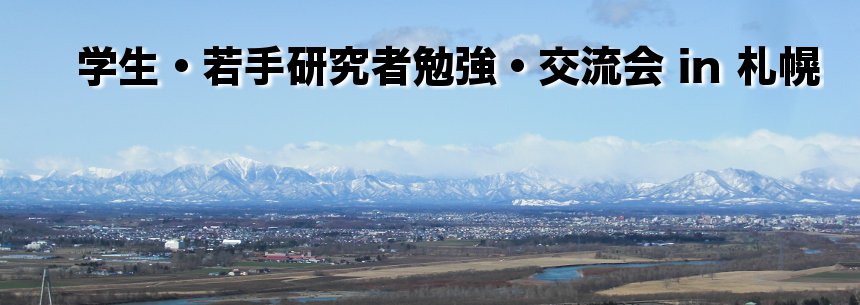過去の活動
南九州 平成16年9月17-20日


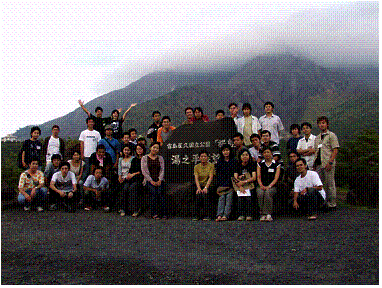


9月17日から20日の3泊4日の日程で宮崎大学・鹿児島大学の共催で行いました。北海道大学、酪農学園大学、山形大学、東京大学、東京農工大学、名古屋大学、京都大学、鳥取大学、九州大学、森林総合研究所、九州沖縄農業研究センターおよび宮崎大学、鹿児島大学から総勢45名の参加者を募ることが出来ました。
1日目はお昼に鹿児島中央駅に集合し、知覧にある鹿児島県茶業試験場を見学させて頂きました。対応していただいたのは環境研究室の内村浩二氏。一般的に窒素施肥量の多い茶の栽培で、「乗用型深層施肥機による低投入型施肥法の確立」に取り組んでおられました。フェリーで鴨池港から垂水港にわたり、大隅湖の畔にある「アジア太平洋農村研修センター」に投宿しました。垂水で温泉に入った後、宮崎大学・鹿児島大学による研究発表会をおこないました。
2日目は午前中、参加者の研究発表会を行いました。一人5分の短い持ち時間を気にかけず、熱心な議論の賜で予定時間を1時間超えて発表会を終了しました。午後は鹿児島県農業試験場大隅支場の見学を行いました。その後、桜島に向かい、湯之平展望台から桜島と錦江湾、鹿児島市を望み、温泉に浸かって「アジア太平洋農村研修センター」へと投宿しました。
3日目は午前中、宮崎県総合農業試験場。午後は日南海岸と青島観光および温泉に浸かって、若手の会最後の宿となる「青島青年の家」に投宿しました。4日目は朝食後、集合写真を写した後、解散となりました。
本年度の若手の会は開催地である鹿児島、宮崎両県の農業試験場などの農業研究の実際に触れ、南九州での農業事情や問題に対する見識を深め、これまでの生産性向上から環境保全型農業の確立へと視野を拡大してきた学問である土壌肥料学研究に課せられている問題点などを認識してもらうと共に、参加者の研究内容の発表および議論を行い、普段、若手研究者が認識する機会の少ない「各人の研究の土壌肥料学での位置づけ」を意識してもらいたいと考えました。さらに、様々な分野の若手研究者のネットワークづくりに役立てていってもらいたいと願い、開催しました。今後も様々な分野の研究を行っている若手研究者が広い視野を持つための交流の場として発展していくことを願います。
山口 平成15年9月20-23日



35回をむかえる若手の会では、山口県セミナーパークで9月20日〜23日と4日間研修を行った。東京大学、鳥取大学、山口大学、九州大学、宮崎大学、鹿児島大学から約30名の参加があった。
初日は、夕方集合し、簡単な自己紹介を兼ねた懇親会を行った。
2日目の研究発表会では、土壌学、土壌微生物学、植物栄養学と多岐にわたる発表が行われ、将来の土壌肥料学を見据えて、終始活発な質疑応答が行われた。また、若くして杜氏となり、酒造りの指揮をとっている永山貴博氏に依頼し、山口県内における酒米「山田錦」栽培の特徴やお酒の基礎知識、農業への熱い思いを講演していただいた。
3日目には、山口県農業試験場を見学し、バラの水耕栽培、pFメーターを用いた養水分管理栽培、特産のはなっこりー栽培、新品種のユリの栽培施設を見学した。研究内容についてだけではなく、実際の研究結果を生かすための流通の確保、費用面での問題も取り上げ、実験室内の研究だけでは意識しないような問題にも触れることができた。午後からは、秋芳洞、カルスト台地を見学し、自然が作り出した神秘を実際に体験した。懇親会では研究の議論や楽しい話で親交を深め合うことができた。
4日間の研修によって、他大学同士の交流を深めることができ、これからの研究の刺激になった。来年は宮崎県にて若手の会が開かれる予定だが、より多くの大学、研究機関の参加者が集まることを期待する。
最後となりましたが、山口県農業試験場 場長角屋正治氏、生産環境部部長平松禮治氏には見学にあたり、大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。
つくば 平成14年8月6-9日

講演「若手研究者に求められる環境研究」 陽 捷行 氏

講演「土壌DNAの利用で広がる新しい世界」 長谷部 亮 氏

土壌モノリス館

温室効果ガス発生抑制施設
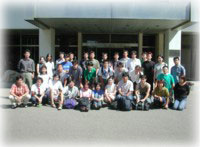
農林水産技術会議筑波事務所前
34回目を迎える今年はつくばの農林水産技術会議筑波事務所国内研修生宿泊施設を利用させていただき,8月6日から9日までの3泊4日の日程で行った。北海道農業研究センター,北海道大学,環境科学技術研究所,筑波大学,農業環境技術研究所,千葉大学,東京大学,名古屋大学,京都大学,鳥取大学,山口大学,九州大学,宮崎大学,鹿児島大学から,研究職員,大学教官,ポスドク,大学院生・学部生約40名の参加があった。
本年は、つくばで開催ということで、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センターに所属する土壌肥料分野の研究者の方々に講演を依頼した。以下に日程の概要を記す。
6日(初日)は夕方に集合し,夕食後、研究内容を含めた簡単な自己紹介を行った。参加者の研究分野は,土壌,土壌微生物,植物栄養を中心に,地球化学,国際環境経済学と多岐に及んでいた。発表時間外にも個別に活発な交流が行われ,参加者の興味と関心を拡げたものと思われる。
7日(2日目)の午前中には,農業環境技術研究所理事長 陽 捷行 氏より「若手研究者に求められる環境研究」,国際農林水産業研究センター理事長 井上 隆弘 氏より,「若手研究者に求められる国際研究」と題したご講演をいただいた。
同日午後は,農環研 化学環境部 栄養塩類研究グループ 土壌物理ユニット 主任研究員の江口 定夫 氏から「現場土壌中の水と溶質の流れ」,同 地球環境部 生態システム研究グループ 物質循環ユニット 主任研究員 新藤 純子 氏から「集水域の物質循環と酸性雨」,同 化学環境部 有機化学物質研究グループ 土壌微生物利用ユニット 研究リーダーの長谷部 亮 氏から「土壌DNAの利用で広がる新しい世界」と題したご講演をいただいた。
同日夜には,参加者3名による研究発表を行い質疑応答などから,参加者同士による活発な意見交換が行われた。
8日(3日目)午前には,農環研 生物環境安全部 植生研究グループ 化学生態ユニット 主任研究員の平館 俊太郎 氏から「これまでの自分の研究をふり返って」,同 インベントリーセンター 土壌分類研究室 主任研究員の大倉 利明 氏から「土壌分類とインベントリー」と題したご講演をいただき,農環研土壌モノリス館を見学させていただいた。
同日午後には,農環研 地球環境部 温室効果ガスチーム チーム長の八木 一行氏から「農耕地土壌から発生する温室効果ガス:発生量と抑制技術」と題したご講演をいただき,温室効果ガス発生抑制施設を見学させていただいた。さらに,同 化学環境部 重金属研究グループ 土壌生化学ユニット研究員の石川 覚氏から「植物の有害金属ストレス、および栄養ストレス研究に関する最近の動向と将来の展望 —特にAl、P、Cdについてー」、同 土壌生化学ユニット 研究リーダーの阿江 教治氏から「土壌中に蓄積するタンパク様化合物の作物による吸収−土壌養分の測定法は正しいのか?土壌肥沃度養分吸収機構について−」と題したご講演をいただいた。各公演毎に活発な質疑応答がなされた。
3日目の夜には,農環研の食堂で懇親会を行った。講演をしていだたいた一部の方々にも参加していただき,参加者、講演者間の交流がさらに深まったと思われる。
最後になりましたが,快くご講演,見学等を引き受けていただきました,上記の方々に深く感謝申し上げます。
また,昨年度は学会より経費の一部を援助していただきましたが,今年度は国内研修生宿泊施設の利用ならびに貸切バス不利用により経費を大幅に低減できたため,援助のお願いを申し出ませんでした。今後とも経費の節減には努めてまいるつもりですが今回のように恵まれた条件で開催できることはまれであると思われますので、今後ともご支援等どうぞよろしくお願い申し上げます。
関東 平成13年8月6-9日

研究発表

神奈川県農業総合研究所

バラ農園

クミアイ化学

懇親会
33回目を迎える今年度は神奈川県の宿泊施設を利用し、8月6日から9日まで3泊4日の日程で行われた。以下のように全国から約30名が集まった。
東北農業研究センター、農業環境技術研究所、埼玉県農林総合研究センター、北海道大学、筑波大学、宇都宮大学、東京大学、東京農業大学、京都大学、山口大学、九州大学、鹿児島大学
6日と7日の夜は一人5分程度で研究発表会を行った。参加者の研究分野は、土壌、土壌微生物、植物栄養と多岐に及んでいたが、同世代ということもあり、わからないことを気軽に聞くことができた。同じ場所に宿泊しているので、時間内に聞けなかったことは後に個別に話をしたりして、活発に交流をすることができた。
7日は神奈川県農業総合研究所を見学させて頂いた。研究所の方々は、特産品の開発や環境保全型農業について熱心に研究をしていらした。所内では様々な分析機器について、どのような研究に使われているかも合わせて説明して頂いた。土や堆肥の成分の測定、栄養診断、植物中の重金属の測定、残留農薬の測定などのために、様々な分析装置があった。また、バイオテクノロジーの研究室では、近年はDNAマーカーが育種に利用されていることをお話して下さった。形や花の色などに特徴を持つ品種を、幼植物の段階で検出することができるので、時間や労力を省くことのできる有力な手段であることを学ぶことができた。圃場では、有機質肥料を併用することによって化学肥料をいかに減らすことができるか試験をしていらした。益虫を用い、農薬の使用を減らすための試験もしていらした。資源リサイクル施設では、生ゴミなどから堆肥をつくる装置を見せていただいた。参加者には堆肥について研究しているものが多くおり、実物を見ることができたことは非常によい機会であった。温室では、病害虫を駆除するために締め切って高温にし、その高温にに耐性の品種を探す試みなどをしていらした。他にも本当に多くのものを見せて下さった。
また研究所の方にご紹介頂き、神奈川県内の石井通生様と鈴野実様のバラ農園を見学させていただいた。石井様は土耕栽培をなさっており、堆肥を用いた土づくりに力を入れていらした。土壌を熱湯消毒するシステムを開発したり、潅水同時施肥をすることによって施肥量をを減少させたりする等、環境に配慮した栽培をなさっていた。一方鈴野様は水耕栽培をなさっており、温室環境をコンピューターシステムで適格に管理していらした。液肥を、途中サンドフィルターを通しながら循環させることにより、施肥量を減らす取り組みをなさっていた。
8日は、農薬の会社であるクミアイ化学の生物科学研究所を見学させて頂いた。初めに、微生物や動物を用いて、農薬の安全評価をしている研究室を見せていただいた。微生物では遺伝子に傷をつけないかどうかが調べられ、動物では血液の成分、皮膚や角膜、ほとんどの臓器への影響、胎児への影響まで調べられていた。動物が犠牲になっていることにショックをうけたが、非常に厳しく様々角度から安全性が検査されていることを知った。温室ではポット栽培などで農薬の試験がなされていたほか、年間を通じて常に試験に使えるように植物が栽培されていた。次に、温室での検査を通過した農薬を試験する圃場を見せて頂いた。多種類の植物に対して試験できるように様々な植物が栽培されており、それらを実際に見ることができただけでも意味のあることであった。暗渠排水や、堆肥を製造している様子も見ることができた。農薬の分解について調べるためのライシメーターもあった。また、農薬が植物や土壌中をどのように移動して行くのかを追うためのRI施設や、分析装置も見せて頂いた。
このように3泊4日の間に私たちは多くを学び、仲間と語らうことによって、研究への活力を得ることができた。この若手の会で得たことを、土壌肥料分野の発展へとつなげるために頑張らなくてはと感じている。
来年以降も土壌肥料若手の会は行われて行くが、より多くの人に参加してほしいと思っている。
神奈川県農業総合研究所の皆様、石井様、鈴野様、クミアイ化学工業の皆様には大変お世話になりました。心より感謝申し上げます。
社団法人日本土壌肥料学会からは、経費の一部を援助して頂きました。誠にありがとうございました。
九州 平成12年8月7-9日



| 内容 |
|
|---|---|
| 参加者 | 26名(学部生 4名、修士課程 11名、博士課程 7名、ポスドク 3名、大学教官 1名) |
| 参加団体 | 北海道大学、筑波大学、宇都宮大学、東京大学、京都大学、山口大学、九州大学、鹿児島大学 |
| 参加費 | 学部生9千円、その他1万8千円 |
| 宿泊場所 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
大分県温泉熱花卉研究指導センターでは、試験研究で行われている、キクやトルコギキョウの育種や底面給水による切り花の栽培、杉皮バークを利用したバラの養液栽培などについて現場を見ながら解説をして頂いた。さらに、同研究室の実験室を見学させて頂いた。ここで開発,栽培された切り花が関東地方にまで出荷されているということや、環境保全型花卉栽培技術の開発などが行われていることなど、一地方で行われている研究の貢献度の高さを知った。
また、日本フェロー株式会社では微量要素の研究がなされており、微量要素肥料の生理的役割の解明、製品の改良と開発についての解説をして頂いた。。同社では、20区画の水田と2種類の22区画の畑での圃場試験が20年にわたって行われており、それらを見学させて頂いた。水稲栽培や畑作物の栽培における3要素や微量要素の必要性が一目で分かり、農業における肥料の重要性を再認識したという声が、参加者から多く寄せられた。また、卒業論文で茶樹の施肥について研究している者は、卒論に関するヒントなどを得ることができた。
北海道 平成11年8月2-5日

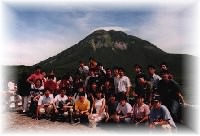

| 内容 |
|
|---|---|
| 参加者 | 32名(学部生 2名、修士課程 22名、博士課程 4名、大学教官 3名、四国農業試験場 1名) |
| 参加団体 | 北海道大学、東北大学、福井県立大学、東京大学、東京理科大学、京都大学、山口大学、九州大学、鹿児島大学、四国農業試験場 |
| 参加費 | 2万5千円 |
| 宿泊場所 | 根釧農業試験場研修館 |
今回が初の試みであった研究発表会も企画当初はうまく行くのか心配されたが、参加者には分かりやすいOHPを準備してもらい、一人5分をいう発表時間では少なすぎる程、発表内容も充実し質疑応答も活発に行われ、研究での交流を深めるという意味で非常に意義深いものとなった。
お問い合わせ先
〒060-0811 札幌市北区北11条西10丁目 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター 当真要E-mail: