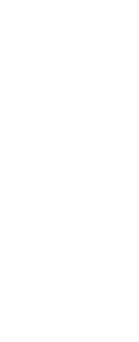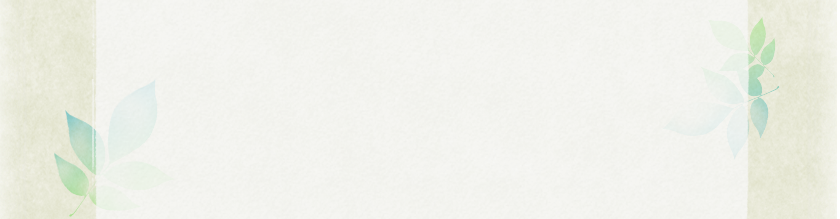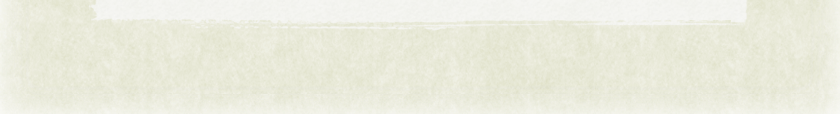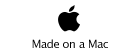圃場の歴史

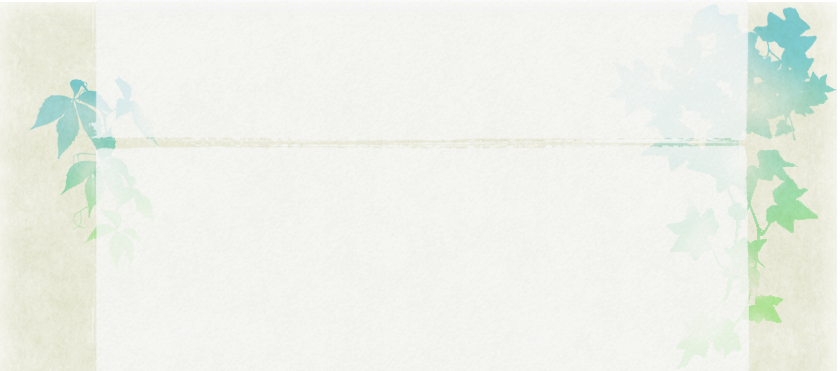
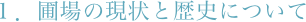
園2圃場は、『園芸学第二(花卉・造園学)講座記念誌』によれば、昭和7年に花卉・造園学の教育研究の場として花卉園が設けられ、昭和11年の講座設置後もそのまま存続し、昭和23年に北大農場園芸第二部として分離されています。その後昭和40年代には、ポプラ並木脇の圃場(通称三角畑)が加わり、花木園として整備されています。
私が在籍していた時期(S49〜52)は、これらの圃場の最も美しかった時代であったと考えられ、ユリやチューリップの試験圃場、芝生や各種グラウンドカバープランツ見本園、様々な花卉圃場や宿根ボーダー、バラ園、花木園と、春から秋までほとんど毎日のように圃場で過ごしていた記憶があります。職員も奥谷、中島、本田さんに加え、臨時職員も数名いたことから、隅々まで十分な管理がなされていた時代でした。
しかし、農場職員の定員削減によって定年退職後の補充もされないまま専属の職員がいなくなり、近年では造園実習による作業や、シルバー人材センターへの委託によってようやく最低限の維持管理を行うのが精一杯という状態となっているようです。H9には花木園が新渡戸記念庭園として本部管理に移行し、また農場も、農学部の組織から「北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション生物生産研究農場」なる全学組織に移行するに至って、有効利用されていない圃場部分は次々と取り上げられてしまい、現在ではかなり傷んだ小屋の回りと、庭園部分、バラ園跡だけがかろうじて確保されているのが実状となっているのです。
また、昨年9月に本道を襲った台風18号の強風により、庭園周囲のトウヒ類がすべて折られたり倒されてしまい、庭園としての価値を大きく減ずるに至って、このまま荒れた状態で置くとやがてすべて取り上げられかねない、危機的な状況に陥っていると考えられます。