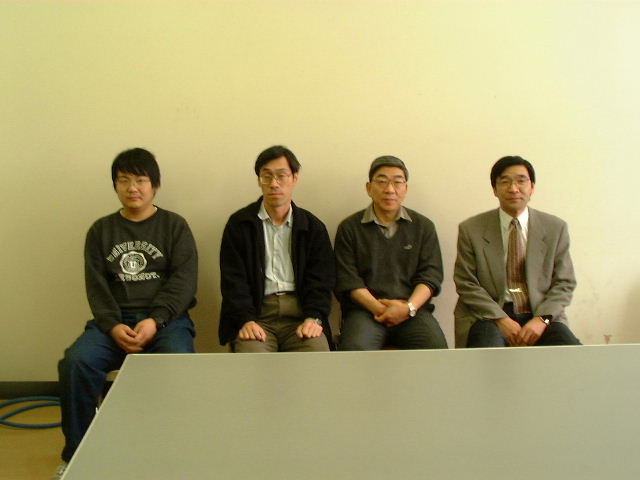| [沿革・概要] 当研究室は昭和51年開設の環境工学科環境制御工学講座が前身であり、平成5年の学科改組と大講座制への移行に伴い現在の名称へと改めた。炭素変換工学は新しい造語であるため一般には認知されていない学問・研究分野であるが、その命名は炭素資源を有用な物質へ変換するための工学技術を一貫して取り扱うことに由来する。前身講座時代の石炭のガス化と木質系バイオマスの熱化学的流体エネルギー化を研究の両輪としているが、名称変更以降は対象炭素源を古タイヤ、廃セルロース製品、リグニン等へ拡げ、廃棄物の再資源化や機能性炭素材料の開発にも着手している。また、最近では本学が推進する産業クラスター構想の下で、地場の林産資源の有効活用を図るべくカラマツ間伐材からの活性炭の連続生産プロセスの開発にも取り組んでいる。 |
|
|
[スタッフ、学生] スタッフは鈴木 勉教授、山田哲夫助教授、船木 稔助手、橋本晴美技官の4名で、本年(平成11年)度の学生在籍数は大学院博士前期課程が5(内中国人留学生1)、研究生が1、学部4年生が11の計17名である。博士後期課程は4年前に設置されたが、在籍者はまだいない。 |
|
|
[研究内容] 対象とする炭素原料で大別すると、以下の3つとなる。 ②石 炭 ③
廃タイヤ、廃セルロース製品、農産廃棄物 |
||
[最近の研究成果] 過去3年間の発表論文は以下の通りである。 |
||
[主要な研究装置、 分析機器類] 比較的大型の装置として高圧熱天秤、常圧熱天秤、高圧気体流通系反応装置、ホットプレス、活性炭製造用連続炭化炉等を設置している。分析機器としてはGC-MS、元素分析計、GPC、ガスクロ等を所有している。その他NMR、X線回折、XPS、レーザーラマン分光装置、FI-IRを学内で共同利用している。 |
 |
 |
| 左写真:ホットプレス(木タール接着剤を用いるパーティクルボードの作成に使用) 右写真:高圧気体流通系反応装置(石炭の高圧ガス化用) |
||
[共同研究等] カラマツ活性炭の連続生産プロセスの開発は本地域の産学官共同研究であり、本研究には当研究室の全スタッフが参加している。リグニンからの機能性炭素材料の開発と石炭の無触媒高効率ガス化では、複数の大学、公立研究機関等で組織されたプロジェクトチームにそれぞれ鈴木、山田が個人として参加している。 |
||
[連絡先] 〒090-8507 北見市公園町165番地 北見工業大学化学システム工学科 |
||