生き物が生きるということは、親から子へと受け継がれる情報に従って多数の遺伝子の発現が正確になされてはじめて可能になります。例えば、ヒトの子はヒトであり、イヌからネコが産まれてきたり、植物の種子を播いたら動物ができてきたりするなどということは起こりません。私たちが経験的に当たり前のこととして受け止めているこのことは、生物の個々の遺伝子および遺伝子の発現を司る情報が正確に次世代に受け継がれることによります。生物の持つ情報が次世代に伝達されることに関して、DNAの塩基配列による伝達機構を「ジェネティック(genetic)」な現象と呼ぶことができます。メンデルの法則にのっとった遺伝現象は「ジェネティック」なものです。それに対し、DNAの塩基配列の変化をともなわない、細胞分裂を経た後も継承される何らかの変化によって遺伝子の活性が変わることを指して、「エピジェネティック(epigenetic)」な現象と呼んでいます。例えば、生物の発生過程では、遺伝子の塩基配列が変わることなく遺伝子の発現パターンが変化して、さまざまな器官が作られていきますが、その機構として、エピジェネティックな遺伝子発現の制御機構が存在すると考えられます。これらと同様に、遺伝現象および遺伝的変異を研究する生物学の一領域を遺伝学(genetics)と呼ぶのに対し、DNAの塩基配列の変化を伴わずに変化する遺伝子機能を研究する領域をエピジェネティックス(epigenetics)と呼んでいます。
私たちは、こうしたエピジェネティックな遺伝子発現の制御機構である「ジーンサイレンシング」と呼ばれる現象に着目し、高等植物を研究材料に用いて、その分子機構の解析を行なっています。ジーンサイレンシングとは、文字通り、「遺伝子の不活性化」のことです。細胞には、ある状況で、特定の遺伝子の発現が行なわれないようにする遺伝子発現の制御機構が存在します。このジーンサイレンシングという機構に世界の分子生物学の研究者が着目する大きなきっかけの一つとなったのは、1990年に米国およびオランダの2つの研 究グループが発表した、植物におけるコゥサプレッション(co-suppression)という現象です。これらの研究グループでは、アントシアニン色素が合成されることによって紫色の花を咲かせるペチュニアに対して、この色素の合成経路の遺伝子の一つを導入し、過剰に発現させるという試みをしました。このことにより、色素の合成系が増強されて、より濃い紫色の花が付くかと思いきや、実際には、予想に反して、紫色の花の他に白色の花や紫色と白色の部分が混在した花を咲かせる植物ができてきました。この現象は、外から加えた遺伝子とその遺伝子と同じはたらきを持った元から植物の中にある遺伝子の両者が不活性化されたことによるものであることが明らかにされ、コゥサプレッションという呼び名が与えられました。その後、さまざまな生物においてコゥサプレッションと類似したジーンサイレンシングの現象が見いだされ、その機構にも共通性があることが2000年前後に明らかにされました。
究グループが発表した、植物におけるコゥサプレッション(co-suppression)という現象です。これらの研究グループでは、アントシアニン色素が合成されることによって紫色の花を咲かせるペチュニアに対して、この色素の合成経路の遺伝子の一つを導入し、過剰に発現させるという試みをしました。このことにより、色素の合成系が増強されて、より濃い紫色の花が付くかと思いきや、実際には、予想に反して、紫色の花の他に白色の花や紫色と白色の部分が混在した花を咲かせる植物ができてきました。この現象は、外から加えた遺伝子とその遺伝子と同じはたらきを持った元から植物の中にある遺伝子の両者が不活性化されたことによるものであることが明らかにされ、コゥサプレッションという呼び名が与えられました。その後、さまざまな生物においてコゥサプレッションと類似したジーンサイレンシングの現象が見いだされ、その機構にも共通性があることが2000年前後に明らかにされました。
ジーンサイレンシングには、大別して2つの機構があることが知られています。一つは、DNAが転写されてRNAができる段階において、転写が阻害され、その結果、その遺伝子の産物(mRNAおよびタンパク質)の産生量が著しく減少して、遺伝子機能がなくなる機構(transcriptional gene silencing: 転写ジーンサイレンシング)です。例えば、哺乳類において父親・母親由来の対立遺伝子の一方だけが発現するように配偶子形成過程で遺伝子がマークされるゲノム・インプリンティングにはこうしたことが関わっています。もう一つは、転写が起きた後に特定の遺伝子のmRNAが分解され、その遺伝子の機能がなくなるという機構(post-transcriptional gene silencing: 転写後ジーンサイレンシング)です。この機構は、植物におけるコゥサプレッションの他、アカパンカビにおけるquellingという現象や、線虫やショウジョウバエで見つかったRNA interference (RNAi)という現象において共通にはたらいているということが、これらの生物種で得られた突然変異体を用いた解析ならびに生化学的な解析から明らかになっています。これらの現象の生命科学における重要性は、1998年にRNAiの現象を見出したAndrew Z. Fire博士とCraig C. Mello博士が2006年にノーベル賞を受賞したことからもうかがえます。
私たちは、ジーンサイレンシングという現象が、どのようにして起きているのかを前述のペチュニアにおける色素合成系の遺伝子の発現を指標にした実験系を中心として明らかにしようと研究を行なってきました。その成果として、外来の遺伝子の転写が不活性化される場合に転写を行なう機能を持つプロモーター配列がメ チル化という修飾を受けること、その場合にプロモーター配列に対するタンパク質の結合が阻害されるといったことや、転写後にmRNAが分解を受けるのに先立ってmRNAが一時的に蓄積することなどを明らかにしています。また、ウイルスベクターを用いたジーンサイレンシングの誘導系を構築し、これを用いてサイレンシングの誘導と維持の機構の解明や、特定の形質が発現する機構の解明を行っています。
チル化という修飾を受けること、その場合にプロモーター配列に対するタンパク質の結合が阻害されるといったことや、転写後にmRNAが分解を受けるのに先立ってmRNAが一時的に蓄積することなどを明らかにしています。また、ウイルスベクターを用いたジーンサイレンシングの誘導系を構築し、これを用いてサイレンシングの誘導と維持の機構の解明や、特定の形質が発現する機構の解明を行っています。
ジーンサイレンシングは、動植物の病原となるウイルスや、トランスポゾンによるゲノム構造および遺伝子発現の撹乱に対して、真核生物が進化の過程で獲得した自己防御機構であるという概念が提唱されています。また、生物の進化を構成する主要な要素となる交雑やゲノムの倍数化の過程においても遺伝子発現の変動が起きることが知られ、そこにはジーンサイレンシングの機構が関わっていることが次第に明らかになってきました。自然界にはジーンサイレンシングが関わる未知の生命現象がたくさん隠されているに違いありません。こうしたことを背景として、私たちは、ジーンサイレンシングに関する研究を主体として、生物の持つ遺伝情報の進化と遺伝子発現機構の進化の関係を解きほぐし、種分化の機構、さらには生物の多様性を理解することを目指しています。また、ジーンサイレンシングの機構を利用して新しい植物遺伝資源を創成し、育種に応用する研究を行っています。例えば、ダイズを対象として、ウイルスベクターを用いたジーンサイレンシングにより生産上重要な形質発現の機構解明を行うことや、新たな視点から人の健康維持に役立つ植物成分を同定することなどの応用的研究を展開しています。
これらの研究に加えて、ダイズの種子貯蔵タンパク質の遺伝子発現制御、ダイズの遺伝的多様性に関する研究、ペレニアルライグラスの耐凍性に関する研究、イネにおける生殖関連形質に関する研究等を共同研究により行っています。
このような観点から、植物の遺伝学や分子育種に関する研究に意欲的に取り組む大学院生を募集しています。
連絡先〒060-8589
札幌市北区北9条西9丁目 北海道大学大学院農学研究院
金澤 章
e-mail: kanazawa.@res.agr.hokudai.ac.jp (迷惑メール対策のため、@の前に不要なピリオドを入れてあります。)
2. 最近の論文から
Koseki, M., Goto, K., Masuta, C. and Kanazawa, A. (2005) The star-type color pattern in Petunia hybrida Red Star flowers is induced by the sequence-specific degradation of the chalcone synthase RNA. Plant Cell Physiol.46, 1879-1883.
RNAiが医療に使える可能性がでてきたことも関連して、ジーンサイレンシングに関する研究は2000年前後からいっそう盛んになりました。ジーンサイレンシングの機構の一つとして、転写後にRNAが塩基配列特異的な分解を受けることは、1990年にカルコーン合成酵素 (CHS) 遺伝子を導入したペチュニアを用いた研究によって明らかになりました。その後、さまざまな生物で、外来遺伝子や二本鎖RNAを導入することで同様な現象がおきることが示されました。では、外来の核酸を導入していない細胞では、こうしたサイレンシングはおきうるのでしょうか?
ペチュニアのレッドスターという品種は、その名のとおり、赤色地に白色の星型の模様の花を咲かせます。園芸植物であるペチュニアの育種は1830年代に欧州の人が南米から持ち帰った野生の植物を交配したことに始まります。レッドスターのような美しい模様を持った植物は、ペチュニアの育種の歴史の中で、その初期から作られていましたが、なぜ、そのような模様が作られるのかは解明されていませんでした。私たちの研究グループでは、この論文で、レッドスターの星型模様の形成が、アントシアニン色素を合成するCHS遺伝子の転写後のRNA分解によっておきていることを証明しました。転写後のRNA分解によって内在性遺伝子の発現が制御されていることを証明した例は(micro RNAによる制御を除いては)このレッドスターの例を含めて、まだ4例しかありません(2007年4月現在)。
この論文は、重要論文を推薦するウェブサイト、Faculty of 1000において、以下のように紹介されています。
“This paper confirms the long-held suspicion that the red and white patterned petals of the commercial petunia variety 'Red Star' result from an RNAi-type mechanism that specifically degrades the mRNA of the pigment gene chalcone synthase (CHS) in unpigmented sectors. Thus, prior to the discovery of cosuppression (or RNAi) of CHS by sense transgenes in petunia, plant breeders selected a naturally occurring case of this important gene silencing mechanism.” (Marjori Matzke, Austrian Academy of Sciences, Austria)
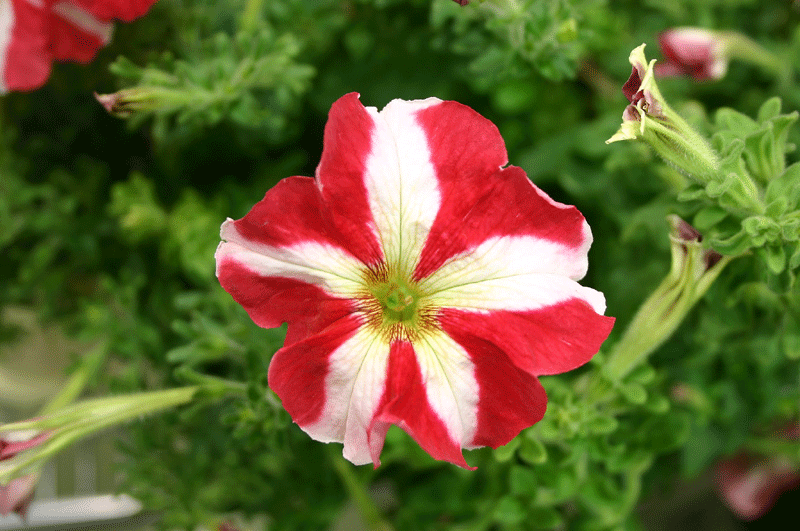
3. 最近の主な研究業績 (2000年以降)
1) 遺伝子の発現調節・遺伝子導入・植物の環境応答に関する研究
Kanazawa, A., O'Dell, M. and Hellens, R. P. (2007) Epigenetic inactivation of chalcone synthase-A transgene transcription in petunia leads to a reversion of the post-transcriptional gene silencing phenotype. Plant Cell Physiol. (in press)
Kanazawa, A., O'Dell, M. and Hellens, R. P. (2007) The binding of nuclear factors to the as-1 element in the CaMV 35S promoter is affected by cytosine methylation in vitro. Plant Biol. (in press)
Otagaki, S., Arai, M., Takahashi, A., Goto, K., Hong, J.-S., Masuta, C. and Kanazawa, A. (2006) Rapid induction of transcriptional and post-transcriptional gene silencing using a novel Cucumber mosaic virus vector. Plant Biotechnol. 23, 259-265.
Shinozuka, H., Hisano, H., Yoneyama, S., Shimamoto, Y., Jones, E. S., Forster, J. W., Yamada, T. and Kanazawa, A. (2006) Gene expression and genetic mapping analyses of a perennial ryegrass glycine-rich RNA-binding protein gene suggest a role in cold adaptation. Mol. Genet. Genomics 275, 399-408.
Yoshino, M., Nagamatsu, A., Tsutsumi, K. and Kanazawa, A. (2006) The regulatory function of the upstream sequence of the conglycinin subunit gene in seed-specific transcription is associated with the presence of the RY sequence. Genes Genet. Syst. 81, 135-141.
Koseki, M., Goto, K., Masuta, C. and Kanazawa, A. (2005) The star-type color pattern in Petunia hybrida ‘Red Star’ flowers is induced by the sequence-specific degradation of the chalcone synthase RNA. Plant Cell Physiol.46, 1879-1883.
Hisano, H., Kanazawa, A., Kawakami, A., Yoshida, M., Shimamoto, Y. and Yamada, T. (2004) Transgenic perennial ryegrass plants expressing wheat fructosyltransferase genes accumulate increased amounts of fructan and acquire increased tolerance on a cellular level to freezing. Plant Sci. 167, 861-868.
Hisano, H., Kimoto, Y., Hayakawa, H., Takeichi, J., Domae, T., Hashimoto, R., Abe, J., Asano, S., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2004) High frequency Agrobacterium-mediated transformation and plant regeneration via direct shoot formation from leaf explants in Beta vulgaris and Beta maritima. Plant Cell Reports 22, 910-918.
Tominaga, Y., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2004) Changes in the structural properties of chloroplasts and mitochondria in response to low temperature in perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Grassland Sci. 50, 31-39.
Abe, J., Xu, D., Miyano, A., Komatsu, K., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2003) Photoperiod-insensitive Japanese soybean landraces differ at two maturity loci. Crop Sci. 43, 1300-1304.
Goto, K., Kanazawa, A., Kusaba, M. and Masuta, C. (2003) A simple and rapid method to detect plant siRNAs using nonradioactive probes. Plant Mol. Biol. Rep. 21, 51-58.
Yoshino, M., Kanazawa, A., Tsutsumi, K., Nakamura, I., Takahashi, K. and Shimamoto, Y. (2002) Structural variation around the gene encoding the α subunit of soybean conglycinin and correlation with the expression of the subunit. Breeding Sci. 52, 285-292.
Tominaga, Y., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2001) Identification of cold-responsive genes in perennial ryegrass (Lolium perenne L.) by a modified differential display method. Grassland Sci. 47, 516-519.
Yoshino, M., Kanazawa, A., Tsutsumi, K., Nakamura, I. and Shimamoto, Y. (2001) Structure and characterization of the gene encoding α subunit of soybean conglycinin. Genes Genet. Syst. 76, 99-105.
Kanazawa, A., O’Dell, M., Hellens, R. P., Hitchin, E. and Metzlaff, M. (2000) Mini-scale method for nuclear run-on transcription assay in plants. Plant Mol. Biol. Rep. 18, 377-383.
2) 植物の多様性と進化に関する研究
Fukuda, T., Maruyama, N., Kanazawa, A., Abe, J., Shimamoto, Y., Hiemori, M., Tsuji, H., Tanisaka, T. and Utsumi, S. (2005) Molecular analysis and physicochemical properties of electrophoretic variants of wild soybean Glycine soja storage proteins. J. Agric. Food Chem. 53, 3658-3665.
Sakamoto, S., Abe, J., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2004) Marker-assisted analysis for soybean hard seededness with isozyme and simple sequence repeat loci. Breeding Sci. 54, 133-139.
Sakai, M., Kanazawa, A., Fujii, A., Thseng, F. S., Abe, J. and Shimamoto, Y. (2003) Phylogenetic relationships of the chloroplast genomes in the genus Glycine inferred from four intergenic spacer sequences. Plant Syst. Evol. 239, 29-54.
Abe, J., Xu, D. H., Suzuki, Y., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2003) Soybean germplasm pools in Asia revealed by nuclear SSRs. Theor. Appl. Genet. 106, 445-453.
Xu, D. H., Abe, J., Kanazawa, A., Gai, J. Y. and Shimamoto, Y. (2001) Identification of sequence variations by PCR-RFLP and its application to the evaluation of cpDNA diversity in wild and cultivated soybeans. Theor. Appl. Genet. 102, 683-688.
Xu, D., Abe, J., Sakai, M., Kanazawa, A. and Shimamoto, Y. (2000) Sequence variation of non-coding regions of chloroplast DNA of soybean and related wild species and its implications for the evolution of different chloroplast haplotypes. Theor. Appl. Genet. 101, 724-732.
Kanazawa, A., Akimoto, M., Morishima, H. and Shimamoto, Y. (2000) Inter- and intra-specific distribution of Stowaway transposable elements in AA-genome species of wild rice. Theor. Appl. Genet. 101, 327-335.