�t�t�z�g�؍L���������S��������

7��3�|9����6��7���Œ����͓������S��������֊w��o�������B����܂ł̊C�O�o���̒��ł��ł����������̂�����̂̂ЂƂƂȂ����B
����̊w��́A���[�������������̂Ƃ��A97�N����͂��߂����W���C���g���[�����V���|�̐V���ȓW�J�i���������Ԃɂ����3�J���ŊJ�Ã��[�e�[�V������g�ށj���݂����̂ŁA��Â͓��{�A�J�Òn�̓t�t�z�g�i�����E�������S��������j�Ƃ����ϑ��I�Ȋ��ł���B��ÐӔC�҂͒{�����̎O�X����A���n�ӔC�҂͋��C����i�ȑO�ɍݒ{�����j�A�����{�����̑��̃����o�[��֘A�w�����T�|�[�g����Ƃ����̐��ł���B�ȉ��Ɋw��؍݂����ނ̒n�ł̑̌��ƈ�ۂ�Y���^�Ƃ��Ďc���B
7��3���i���j
����芷������
��Δ��A���c�s����ANA�ւ�7�F45���B���̉��ɏZ�ނڂ��͕K�R�I��5���������ɂȂ�B����̑����͂c�Q�̎R��N�B193�����̔ނ͐l���݂̒��ł��e�Ղɔ��ʂł��郉���h�}�[�N�^���[���B�����ɂȂ��Ĕނ̑��O���ꂪ������ł��邱�Ƃ������A�ɂ킩�ɐS�����Ȃ�B���c�ŊC�O���s�ی��ɓ���i�͂��߂ăv���~�A�����ł͂���j�A�����k���s���֏�荞�ށB
�Ƃ��낪�o�������ɂȂ��Ă���s�@�͓����Ȃ��B�A�i�E���X�ɂ��ƒ��N�������̍r�V�Ŗk����`�����ւ��ҋ@���Ă���A���ԑ҂���ԂȂ��ߗ������Ђ����Ă���Ƃ̂��ƁB�������Ƀt�t�z�g�܂œ��邽�ߖk���ł̏�芷����2���Ԓ��x�����Ȃ��B��芷�������ԂȂ�������́B1���Ԕ�������Ő��c���B������芷�����Ԃ�30�����܂肵���Ȃ��B�����R����ŊւȂǂɗv���鎞�Ԃ��l����A�E�g���B100���ϔO���Ĕ�s�@���~���Ƃ��������ɒ����C�O���s�Ёi�߃c���̒�g�Ёj�̐E�����l�ƎR��̖��O�����������������đҋ@���Ă����B��l���m�F����ƁA�����Ȃ�u����I�v�Ɩڔz������B�k����`�̒ʘH��3�����E�e�̂��Ƃ�����ʂ����B
�����R���B�N���[�p�̃u�[�X���p�p�b�ƒʂ蔲����B�p�X�|�[�g��������Ƃ݂ăn���R���������B�����łقƂ�ǂ̊O���l�̗��ǂ��z���B���̂��ƃt�t�z�g�s���̃`�P�b�g�������Ƃ�i���łɃ`�F�b�N�C���ς݁j�B��l�Ƃ��@���������݉ו������������̂��K�������B�Ŋւ͂Ȃ��悭�킩��Ȃ��E���ʘH�Ńm�[�`�F�b�N�ʉ߁B���ɍ�����������ւނ����B���̊Ԃ����Ƒ���B6������T�P�Ŏ��O�c�X�ь����ŃW���M���O���Ă�̂ŏ��������B�Ȃɂ�����ĂȂ�������A�܂������Ȃ��f���Ă����B
������������ŁA��̂i�`�k�Œ����Ă����������Ƌg��N�i������j��ǂ��z���B�u�Ȃɂ���Ă�B�������Ȃ��Ə��x��邼�I�v�Ɣ��j��������B�܂��E���p�̃u�[�X����w���������ʂ��A�t�t�z�g�ււ̃o�X�i�ŏI�ē����j�ɂȂ�Ƃ��Ԃɍ����B�劾�̒������s�Ђ̔ނƈ��肵�A�o�X�ւ̂肱�ށB������I�܂����Ԃɍ����Ƃ́B���̊ԂȂ��20���B�t�t�z�g�ւ͂����ɂ͏o���A�����̒x�ꂽ��q��҂��Ă����B�Ȃ�Ƃ����͑S����{�O��JAL�ł������{�l�Ƃ������������Ă����B
�t�t�z�g�܂ł�1���Ԃ̃t���C�g�B���Ȃ�̗��C�������������A���������B��`�ɂ͋��C���o�X�Ō}���ɂ��Ă���Ă����B��������4�����鏺�N�z�e���ցB���̒��ł͍ō����̃z�e���̂ЂƂŁA�R�삭��Ɠ����ƂȂ����B��͂����������ʎq�œ��Ñ�w�̋��������̂��U���Ń����S�����������������ɂȂ����B�R�삭��݂͂�����`�����͂���ЂƂ�^�N�V�[�ŗ[�H�ɍs�����B���̂ւ�͍s���͂�����]���ł���Ƃ���ł���B
�����S�������͂͂��߂Ɋy�c�i15�����x�j���e�[�u���ɂ��Ċ��}�̉S���������A�n�������ʼn��B���̍ہA�E�̒��w�Ɏ������A���̏ォ��V�ɂ܂��B���Ɏ����ɂ܂��B�����Ĉ�C�Ɉ��݊����B���ꂪ��H�̎n�܂�B���Ƃ͗r������̂Ƃ������X�̎M�������ꂽ�B��䥂ł����r������i�ł������B��������ł������p�C���͋��B���d�ɒf�����B�������ď����̏�芷�����ɑ�\�����h�^�o�^�o���̖��͐��Ă��Ƃ��ꂽ�B
 �@
�@
7��4���i���j
���t�t�z�g���T���ƍĉ
�w��͍�����16������J���B�������f�X�N�₻�̑��̔z�����߂Ȃǂ̂���14���Ƀ��r�[�W���ƂȂ����B���̎��Ԃ܂ŋ삯���̃t�t�z�g�ό��ɂł������B�R�삭����O�d��̏��䏕�����Ɠk�����ɂ�����Ô����فi15���j�ւł������B���䎁�Ƃ��挎�̃\�E����K���ɂÂ��s�����Ƃ��ɂ��ʐ^�ɂ����܂邱�ƂɂȂ����B�P�e�Ƀ}�����X�⋰�����i�W�{�A�Q�e�ɃW���M�X�J�����͂��߂Ƃ�����c��̋L�^�A���Î�����̗��j�̓W�����������B���j�W���ł͊��S�ɓ��{�͈��҈����ŁA�����������Ԃ������H�R�̊���X�I�ɓW������Ă����B�̂Ȃ��Â������ŁA���͂��Ȃ菋�������B

���Ô����ق̋������i�W�{�i���v���J�j���{���͏d���ēW���s�\
�z�e���ɂ��ǂ�A���̂����ׂ��ꏊ���t�����g�ł����B�t�����g�ʼnp�ꂪ������x�ł���̂́A�Z�����ЂƂ�ɁA�o�����ЂƂ肾�B�叢�Ƃ����`�x�b�g�����̎��@�ɂ������Ƃɂ����B�^�N�V�[���������A������Ƀ{����Ȃ��悤�ɋA��̓z�e���̓�����ɂ��A�{�[�C�ɒl�i�������Ă��炤���Ƃɂ����B
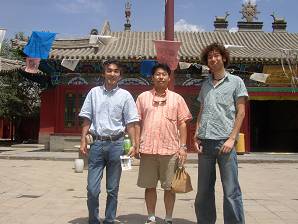 �@
�@
�`�x�b�g�������@�Ƃ��̎����E�G
�叢�i�_�[�W���I�j�܂�10���B�������������ς����āA�܂Ƃ����Ă����B�������Ă�Ɓu���I�[�v�Ƒ吺�������ĈЊd���Ă���B���ꗿ15���B������̃K�C�h�������������ς�킩���B���͋C����������ĊO�ɂł��B���@�̂܂��ɂ͓��{�Ō����u�����v�����B���Ă���A�����ނ��̃��V���A�G�݉��A�������A����Ȃǂ�����ł����B�Q�|�R���i30�|45�~�j���x�Ń��V��������̂Łu�H���Ă��H�v�Ƒ��k�������A�̉��Ȃǂ����킢�̂Łu��߂܂��傤�v�ƂȂ����B�̂̓h�u�l�Y�~�̜p�j����N�A�������v�[���̉���ŕ��C�Ŕт����Ă������ɁB�Ƃ����؋����B�K�^�K�^�̃^�N�V�[�Ńz�e���ɂ��ǂ�A�Q�e�̃��X�g������20���̒��т��Ƃ����B�ߌ�͂��悢��w����B��t�̐݉c�A�z�z���̐����ȂǁB�����������邤����16���̊J����ނ������B
3�J���̑�\�ɂ���u���A���̂��ƃ��Z�v�V�����B�����̃e�[�u����3�J���̎傾�����l�����ƍ���B�����̎Q���҂͂��Ȃ�ϋɓI�Ɂi�Ƃ�����苭���I�Ɂj�������ɂ���B�ڂ����C���m�C��̃}�b�L�[�����i�ȉ����b�h�j��������̂ɋ�S�����B���̌�ʎ���night
mixing�B���b�h�Ɖ�����̃r�r�A����3�l�Ń��C�������B�C���m�C�؍ݎ��̂��ƁA�|�X�h�N�Ōق��Ă�����Ă��鏬�r�N�̂��ƂȂǁA�y�������Ԃ��������A�ӂ�ӂ�ŕ����֖߂����B���̂܂ܗ��ł˂Ă��܂��B���ꂪ��X�������̂������ƂɂȂ����B

���b�h���r�r�A���ƈ��ށB
7��5���i�j
�����ׂЂ��ƌ������\��
���N����Ƃ̂ǂ̉��Ɉ�a���B����B���ׂЂ����B
���H�͂܂��o�C�L���O���B�����͊y�����������A������ɂ����A�ڋʏĂ��͗g�����A������u�߁A�Ɩ��U�߂��B���܂��ɃR�[�q�[���Ȃ��B���{�ł͓���3�t�ȏ�̂ގ����ɂ͂炢�������B
�ߑO���ɏ��сA�R��̌������\���������B���т́u�|�{�s�\�ۂ̐��ԁv���A�R��́u�쐶�G�]�V�J�̃��[�����ۑp�v�ɂ��Ă���ׂ����B�l�̂ق���M1�̌㓡�N�̎d�����܂Ƃ߂����̂����AIGER(�p)��Kim��������@�_���ꂽ�B�R��͂Ȃ�ƃ��b�h����@�ە����y�f�����ɂ��ĕ����ꂽ�B����ɓ싞�_���Zhu�������̐H���������Ă����B�y�f�����ɂ��ĎR��͑����Ă���f�[�^�͂����Ă����̂����A�܂Ƃ߂Ĕ�I���Ďw�j�������ɂׂ͉��d��������������Ȃ��B�ނ͏��߂Ẳp�ꔭ�\�ŋْ������������A�S���ËL���A�����̂��̂ɂ��Ă���ׂ��Ă������߁A�w���ɂ��Ă͂悭������Ƃ�����B���܂Ɍ��e�x�b�^���̔��\���݂邪�A����͂����Ȃ��B��M���`����Ă��Ȃ��B���A���e���Ȃ��Ȃ�����ǂ�����̂��낤�H97�N�ɃW���C���g�V���|������A�l�����͊w���ɉp��������\���ۂ��Ă����B��{�p���͉����݂��ɂ�邱�Ƃ��B������̂�����Έ��S���낤���A����ł͂��܂ł����Ă���B���Ȃ��̂͗��j�������Ă���B����͒��N�w�ɂ������Ӗ��Ńv���b�V���[��^���Ă���B�w�������e�Ȃ��ɂ��̂ŁA�搶�����e�ɗ���킯�ɂ͂����Ȃ��B���N�����ɑ؍݂��ă��A���^�C��PCR���w��ł������\�E�����Sung���́A�����������Ă����T���v����S�ĕ��͂����[�����ۂ̕t���Ƃ�H�̊W���܂Ƃ߂Ĕ��\�����B����͂��łɓ��e�_���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���A�l�������҂̂ЂƂ�ɉ����Ă���Ă���B
 �@
�@
���тƎR��̍u��
���H���ɂR�J����\�҉�c��������B����̊J�Òn���߂ƊT�v�̊m�F���B�����ōj�������n�܂����B�������́u�����ƎQ���҂������邩������ɂ��悤�v�A�؍��Ɠ��{���́u�P�����̉��ŖȖ��ɂ��A������Ă�v�Ƃ����V���|�̌��_��O�ʂɂ������̂ł������B�k���̒����_�Ƒ��Feng���͂��Ȃ苭�d�Ɏ咣�������A�\�E�����Ha���������_�m�F���J��Ԃ����B�l��������̂悤�ɗv�]���������B���ǂ͌��_���d�������Ɏ�Îґ��ɂ܂����邱�ƂɂȂ����B����2007�N�͟��]���Liu��������Âł�邱�ƂɂȂ����B�ނ璆�����́A�؍�����{�ŊJ�Â���Ƃ������̂悤�ɑ����̎Q���҂𑗂荞��ł���邱�Ƃ����҂��āE�E�E
�����͒��A���A��ƃz�e���̓������X�g�����œ����o�C�L���O�������B�R���ڂɂ��Ă����O�����B�����̐���������o�Ă��Ȃ��̂łǂ��������Ƃ��Ǝv���Ă���A���������ĐQ���炵���B����ς�ȁE�E�E�����͍d�������A���낢��s���Ȃ̂Ń~�l�����E�H�[�^�[���Ă̂݁A����ɔ����A��������������������B�ł����{�l�Q���҂̑��������̑؍ݒ��ɕ������������B�ڂ��͎��Q�̃v���o�C�I�e�B�N�X�p���Ȃ�Ƃ��Ȃ������A�������͏d�ĂɂȂ�A���ɗ����ɂ͕a�@����ɂȂ����i�_�H��2�{�����ꂽ���ƃz�e���Ő×{�ƂȂ����j�B�ނƓ����̉@���g��N�̂��Ȃ��ȊŌ�͊������̂������B
�|�X�^�[�Z�b�V�������͋ɂ߂Ă��܂������B�ЂƂƂ���݂āA�L���ɂł�ƁA�������\�̃����e�N�i�\�E����j�ɂ��܂����B���߂Ă̔��\�ŋْ����Ă���炵���A�Ƃɂ����N���ɃR�����g���ق����悤���B�ނ̌����̓��[�������̗ǔۂ��u�_�x�v���w�W�ɂ����ȈՌ������B����̓W�J�������ŁA����̕]�����ς�邾�낤�B�Ƃɂ��������b�N�X������悤�z�������i����j�B
7���U���i���j
���y�����Z�b�V�����ƎЌ���
���͓����o�C�L���O�������̂ŁA�o�i�i�Ƃ����ł��܂����B�ߑO���͔�䍓����̕ʃZ�b�V�����i�\�t�@�̂����c�����j�Ő������̑���ō�����������B����̊w����c�N�̌�̒��Ǔ����y�A�O�d��̏��䂳��̃_�`���E�̋ۑp�A�k��͏�c����̃E�}�̏������R��S���ł��������A�l�I�ɍł��y���߂��B���b�h��N���X�����Ă���Ă��Ċ����Ȏ��₪��������яo���A�܂����䂳��u�����̃��b�h�ւ̌l�I�₢�����Ȃǂ�����A�������͋C�ŏI�n�����B��͂�L�������A���肪�߂��A�c�_���[�܂��Ă悢�B
�ߌ�̓����e�N�̔��\�������A���サ�A�悤�₭�w����t�B�i�[�����}�����B��Ƀt�F�A�E�F�����Z�v�V������������B�l�͏��ւ��O���l�̃e�[�u���ɉ����A��c���A�����ĐȂ��O�����s������L���܂ł���u�����قڑS�������Ă��ꂽ�ނ�̃v���t�F�b�V���i���Ɍh�ӂƊ��ӂ�\�����B�����̋��F�i�؍��j��V�����F�l�i�����j�Ƃ̎ʐ^�ɉ�������B�W�����E�E�H���X�i���E�F�b�g���E�p�j�����C�Ȃ������̂Ŗ₤�ƁA�Ȃ�ƈݒ���������Ȃ��炵���B�W�����̓r�X�P�b�g�Ƃ��������ő��X�ɕ����ɖ߂��Ă������B�R��͎t���̂����������A�i�I��I�Ȃ�����j�Ќ��ɂ�����Ă����悤���i�ʐ^�Q�Ɓj�B
 �@
�@ �@
�@
���]��Liu�����O���[�v���N���X(CSIRO�E��)�Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@���]��Liu�����O���[�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�싞�_�Ƒ�Zhu�����z���̊w��������
 �@
�@
�\�E����̒m�ȂƁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R��͟��]���Guo��ƃc�[�V���b�g�@
7���V���i�j
���������S���呐���ց�
�Z�������������B�����̓G�N�X�J�[�V�����Ō��w�{�呐���c�A�[�B�o�X�ł܂��t�t�z�g�x�O�̖��̍H�ꌩ�w�B���i�u�������イ�v�ł͂Ȃ��u����ɂイ�v�j�͓������S������������_�Ƃ���������i���[�J�[�ŁA��N�́u����������Ɓv�̃g�b�v�ɑI�o���ꂽ�B���X�u�ɗ��v���ƊE��ʂł��������̂́A�ŋ߂͖��̃V�F�A���������Ă���B�O�]���ǂ���A��K�͂Ő������ꂽ���Y���C���ł������B�����Ŗ�P���Ԃ��������B
 �@
�@
���H��̐��Y���C���Ǘ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�X��������������}�[�{�[�����i�}�[�����������j
���ō���̃n�C���C�g�ł���O�X������́u���[�̖���߂����呐���v�������B�r������������T�[�r�X�G���A�i�H�j�̃g�C���́A�������i�H�j�Z���ŁA�ΒY�^���Ԃ̉^����Y�ʼn��ꂽ�g�̂���Ȃ̂��A�������ɂ����̂��A���f�����˂��B�����ȕn���������������ʂ�߂��A��S���ԂŖړI�n99 Springs�ɒ����B�����͕����ʂ�99�̐���Ƃ��E�E�E�Z�����n�����܂ōL���邳�܂͓��k�̉����������A�z���������A�K�͂ł͂�͂肩�Ȃ�Ȃ��B�o�X����~���ƃ����S�����̂��o�}���i�y�c�Ƃ����j�B�����ɗr����̂̒��H�ƂȂ����B�����ŏo�Ă����}�[�{�[�����ɎO�X�������B�g�C���ɂ�������ł������B�����͊C��2,000�����x�����A�̎��I�ɕq���ȏ��䂳��͍��R�a�Ɏ����Ǐ�ő������p�I�i�e���g�j�̒��Ń_�E���B
���̌�A��n�Q���ԃR�[�X�i120���j�łT�����قǐ�̏W���܂ł����B���ւ��O���l���̂����A�قƂ�ǂ̓��؏o�Ȏ҂�����ɎQ�������B�E�}�͖k�C���a����v�킹��|�j�[�ŋɂ߂ĉ����B���n�l�ɂ������E�}���������A��]����g���b�g��M�����b�v���\���B�E�}�Ƃ��̈������������肩�Ȃ���S�ȃc�A�[���B���������Ƀ`�b�v��v�����ꂽ�B�T���������B�A����A�\�E����̏��q�w���~���W�A�f�����Ƃ���ׂ�B��l�Ƃ��������悭�ł���w���i�~���W���@�ەt���ۂ�PCR��ʁA�f���������̖Ɖu�����j�����A�p��b�����Ȃ�̂��̂��B�炿�̂������삳��Ƃ�����ہB���̌�z�[�X�V���[�ƃ��X�����O�B���X�����O�ɂ͓��{����͍��R�a���畜����������̏��䂳��A�؍����烆���e�N���ł��B���䂳��͍ŏ����������������������̂́A������ɂȂ������̉^���s���̂����Őɔs�B�����e�͌��n�l�̃`�����v�Ɍ����������A���т𗁂т��B�����A�ǂ����Ō�͂��������V�i���I�Ȃ̂����E�E�E
 �@
�@ �@
�@
��n�c�A�[�ɎQ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�E����EHa�����v�ȁA�L���鏑�A�f�����A�~���W�@�@�@�@���䂳�����S�����o�ɒ���
�f�B�i�[�͗r�̊ۏĂ��B���Ȃ��݂̊y�c�Ɣn���B���ׂ��������������̂ŁA���C�����K�o�K�o����ő��߂ɋx�B�O�ł͒E���Ǐ畜�������������̃_���X����I���ꂽ�悤�ł݂Ȃ����������炵�����A�������Ă��܂����B�܂�������͂��ߎ傾�����l�����͖�̍X����܂Ŏ��[�̐�����y�����悤�B
 �@
�@
�q�c�W�̊ۏĂ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̃����o�[�œ����p�I�ŐQ�܂���
7���W���i���j
���E�o�Ƃ������̋A�r��
�u������Q����g�C����������v�Ƃ������搶�̒��̈��A�B�ڂ����g�C���ɂ������烍�b�h�������B�S���̃V�J�S��c�ł́u�R�o���V�v�u�}�b�L�[�����v�Ƃ��݂��Ăэ����Ă������A����u���X�v�u���b�h�v�ƌĂэ����钇�ɂȂ����̂����n�̂ЂƂ��낤�B�W�����͈ݒ�������ǂ��������炵���B�r���̒����͂�̂��ƁA�r��̃V���[�����X�g�����̗��ł��Ƃ����M�����Ȃ��V�`���G�[�V�����B�܂��u�z�����a��v�̎c���Ȃ̂���������B�u�L���[�v�Ƃ��������w�B2���ڂ������S�����̕��o�o�R�哮��������B����͕��ɏ��������������A��������������A�w��ő哮����T��A�������ĕ��o���ɑ�ʏo������������B�O�Ɉ�،����łȂ��B���o�ɂ��܂��������ł܂�������ɉ�̂���̂ŁA�Ìł������t�͗����Ɏg����B�P���ڂ͂Q���ڂ̂��炵�������킾�����邽�߂̑ΏƋ悾���A�����猩��ɂ͏d�������B���傤���Z�L�ƕ@���B
��������Ă���Ă����{���M�̌������b�h�A�W�����A�N���X�ɑ��k�B�����͂��ł�AJAS���烌�r���[���M���˗�����Ă���悤�����A����Ƃ͕ʌ��Ƃ������Ƃŗ�������������B��̑ފ��L�O�����˂Ă���̂ŁA���ƂP�N�������Ȃ��B���̊ԂɎ��M�҂Ɠ��e����A���e�����A�ҏW�i���̑��̓���j�Ȃǎd�����R�ς��B���̂ق�Ha�����ɂ��������Ƃ�����B
�o�X�ň�H�t�t�z�g�ցB�Ƃ��낪���ԓI�]�T���������̂œr���y�Y�����֊��ꂽ�B�c�A�[�̍Ō�ł͂��肪�������A���̂������Œ������킽�������Ȃ����B����ɏ��ւ��O���l�����Ƃ����ʂ�̈��A��������Ƃł��Ȃ������B�ߌ�̃t���C�g�ŋA����{�l�̓z�e���߂��̃��X�g������20���ŋ}���̃����`�i�Ȃ�Ɩk���_�b�N�j�B�����`���V�����[��I�R��́A�����H�������˂Ă��܂����B��`�ł̓R�[�q�[�V���b�v���݂������A�u���}�����Ȃ��200���B�؍��O���[�v�Ɠ����t���C�g�������B�����͖k���łQ������炵�����łɏC�w���s�C���B�@���̐V���Ń����h���ł̓��������e����m��B
�k���ɂ͒������s�Ђ̏o�}��������A�l�A�R��A���A�_�H��̃��[�}���N�A��������̂T���Ŏs���̃z�e�����ϔѓX�ɂނ����B�����͓��q�n��̃z�e���ł����Ԃ���K�B�t�t�z�g�Ƃ͂���ׂ�ׂ����Ȃ��B�V���|�ɓW��������Ă������{�S��̊p�c�����i�S��ō��z���̌����͓V�Õt�߂̊C�݂łƂ�j�Ɨ[�H���Ƃ��ɂ���B��C����o�X�����L�����̓X�u����C�N�v�ŃR�[�X�ɂ̓t�J�q����A���r���łĂ����B�����������̂��A�A�q���̎��B����͎����̂��̂��_�炩���ύ���ł���A���܂ŐH����㕨�B�悭�₦���r�[���ŁA���𐁂��Ԃ����B�X���ł�ƃX�^�[�o�b�N�X�Ȃǂ�����A���͂Ⓦ���Ƃ����Ȃ��B���z�r��̃r�����������A�k���̔��W�͖ڂ��݂͂���̂�����B

�k���ŐH�������������i���オ���������A�E�オ�A���r�A�����A�q���̎��j
7���X���i�y�j
�����ҁ�
���낢�날�������ŏI���������B�܂�������D���������R�삾���A����̗[�H�ŃQ���b�����悤�B�A���r����������ˁA�R��B�n�R�������H���̑����t���C�g�ł������Q���ԑO�ɋ�`�ɂ��˂Ȃ炸�S:50�N���B�z�e���ł����Ƃ������{���̒��H�o�C�L���O�i�[���܂ł������j���Ƃ�A��P�T�Ԃ�̃R�[�q�[���̂݁A��H�k����`�ցB�V������`�łQ���Ԃ��y���ށB���X�ƕ��ׂ��Ђ��A�{���̃A�N�e�B�u�ȎЌ��͂ł��Ȃ��������A�Œ���̎d���i�R��̏Љ�A�V���|�̕����Â��A�{���M�̍��A���F�Ƃ̐e���A�����̊֘A�����҂Ƃ̌𗬊J�n�j�͂ł������Ǝv���B����ɂ��Ă���ꂽ�B���炭�C�O�͍s�������Ȃ��Ǝv���B�E�E�E������������܂ő������낤���B����ς���������œ싞�_��K��◈�N�̉p���W���C���g�V���|�o�Ȃ̖����Ă��܂������E�E�E�B�t���C�g�͏����ŁA���c������H�c�܂ō����o�X�A��ɂ����͖̂邾�����B�����h�g���H�������B